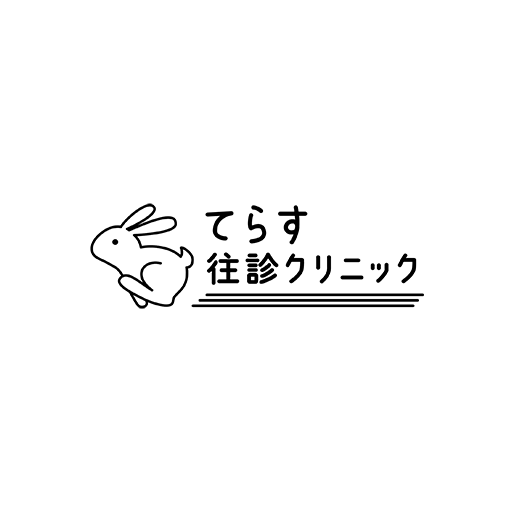当院で満たす施設基準及び加算に関する掲示
診療明細書の発行について
領収証とともに、詳細な医療費の内訳がわかる「診療明細書」を発行させていただきます。発行にかかる費用は無料です。ご不要な方はお申し付けください。
- 診・再診料
- 注射:投与した薬剤名
- 投薬:投与した薬剤名
- 検査:血液検査などの項目
- 画像診断:X線検査などの項目
外来後発医薬品使用体制加算について
当院では先発医薬品より安価で同等な後発(ジェネリック)医薬品を推進しており、後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っております。
後発医薬品とは、先発医薬品と同じ成分を含むものであり、同じ効果が期待できます。患者さんへの医療費負担を軽減し、かつ先発品と同等の治療が期待できます。また医薬品供給不足が発生した場合には、患者さんに必要な医薬品を供給するために、以下のような対応を行います。
- 用量・投与日数の変更…医薬品の用量を調整することで、現在の処方量での治療を継続することが可能な場合があります。医師が患者さんに適切な用量を決定し、医薬品を調整します。以上のことを踏まえ、薬剤の「商品名」ではなく「一般名」を記載する院外処方箋を発行することがあります。
- 代替品の提供…供給不足のある医薬品に代わる、同等または類似の効果が期待できる、別の医薬品を提供します。
一般名処方加算について
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名(商品名)を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
医療DX推進体制整備加算について
医療DX推進体制整備加算は、医療機関が医療DX推進体制を整備することに対して支払われる診療報酬加算です。当院は、医療DX推進体制整備加算を算定し(2024年9月より)、医療の質の向上と効率化に取り組んでいます。
当院の取り組み
- オンライン資格確認の導入
- 電子処方箋の発行(電子カルテベンダーの対応が済み次第導入予定)
- 電子カルテ情報共有サービスは、2025年の本格運用開始以降、可能な限り対応する予定です
医療DX推進体制整備加算のメリット
- 患者さんの診療に歳する待ち時間の短縮
- 医療従事者の負担軽減
- 医療安全性の向上
関連資料
- 厚生労働省「医療DX推進体制整備加算算定要件及び施設基準」
- 日本医療情報学会「医療DX推進体制整備加算に係る施設基準の解釈指針」
医療DX推進体制整備加算・在宅医療DX情報活用加算について
- 当院は医療DX推進体制整備加算および在宅医療DX情報活用加算の届け出を行っています。
- 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を閲覧・活用し診療を行っています。
- マイナ保険証利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
- 電子処方箋の発行や電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取り組みを実施して まいります。(今後順次導入予定です)
在宅医療情報連携加算について
- 当院においては、在宅医療情報連携加算体制について、以下の整備を行っています。患者さん同意の上、状況に応じて以下の連携する保険医療機関・介護施設等との間においてICTツール(モバカルリンク)を利用することで、患者さんの診療情報等を共有して常時確認することができます。よりきめ細やかな在宅医療を提供すべく、連携体制を強化しています。
訪問看護医療DX情報活用加算について
- 当院においては、みなし指定(健康保険法の保険医療機関としての指定を受けている病院・診療所が、介護保険法における訪問看護の事業者として指定をされたものとみなされること)訪問看護事業者として、より質の高い看護を目指し、医療DX推進体制に取り組んでいます。
- 健康保険証と一体化したマイナンバーカードを通して、オンラインでの資格確認を行っています。取得した資格情報をもとに、電子処方箋システムや電子カルテ共有サービスとの情報連携を行い、医療情報を活用した訪問看護を行います。
発熱患者の受け入れについて
当院においては外来診療において、患者さんの受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑うような症状を呈する患者の受入れを行う旨を公表し、受入れを行うために必要な感染防止対策として、発熱患者等の動線を分ける等の対応を行う体制を有しております。
ただし当院かかりつけの患者さんの中にはご高齢の方や基礎疾患を有するなど、感染に対する抵抗力の低下した方がおられます。
一般患者と発熱患者の動線を分ける必要があるため、発熱のある方は必ず事前にご連絡をお願いいたします。
時間外対応加算1について
当院を継続的に受診している患者さんからの電話等による問い合わせに対し、常時対応できる体制を取っております。
診療時間外には、かかりつけ患者さんから当院へお問い合わせは、あらかじめお伝えしている 夜間・休日専用番号に電話をおかけください。
他の患者さんの対応中や、往診中、往診車の運転中などのため、即座に対応できないことがあります。その際はおかけいただいた電話番号に折り返し連絡いたします。